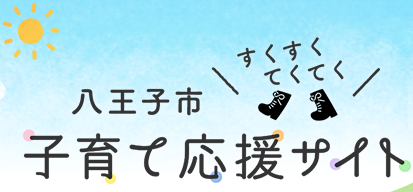11月27日(木)② 特に、「学びに向かう力」を正しく伝えるために(教員研修、通知表、適正な評価)
- 公開日
- 2025/11/27
- 更新日
- 2025/11/27
学校長より
通知表では、どの教科でも、「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力等」「主体的に学習に取り組む態度」の3観点での評価をお伝えしています。
「知識及び技能」と「思考力〜」はワークテストや小テスト、ノートの記述等を根拠として評価できるので、子どもたちも保護者も、あまり疑問をもたないかと思います。
一方、子どもたちと保護者に学校の意図が正しく伝わりづらいのが「主体的に学習に取り組む態度」です。
この観点は、各学年の発達段階に応じて、子どもたち一人ひとりが自分の学力を客観視(メタ認知)して、自分の学習の「量」と「質」を調整できることについて、指導と評価をします。
高学年の漢字の定着だけを例にとると、テスト前日にドリルを一通り20分で書き直して96点が取れた子はA評価な一方、3日間にドリルを等分して20分ずつ取り組んだけど、1日目、2日目の記憶が定着せずに80点だった子はB評価なのが原則です。後者の方が学習量は多いのですが、「2日前以前の記憶が残りづらい」という自分の特性を見つめ直し、学習の仕方を調整しないと(質を高めないと)Aにはならないのです。
「主体的に学習に取り組む態度」が評価される子は、「知識〜」も「思考力〜」も伴って高いはずという考え方が、現行の評価のあり方です。(数年後、学習指導要領というものが改訂される時には、この観点の評価はABCではなく、記述式になる方向とのことです)
評価についての校内教員研修後、職員室の先生たちの会話を聞いていると、「学習指導要領の理屈は分かる。けど、頑張りがなかなか成果に結びつかない子の評価を下げてしまうことが、子どものモチベーション低下につながってしまうのではないか」というジレンマに悩んでいることがよく分かります。
教員は、このように研修をくり返しながら、適正な評価(裏返しての適正な指導)のあり方についての妥当性をすり合わせています。
大切なことは、通知表を通して、学校と保護者とが正しくお子さんの現状と今後の手立てを共有することです。そのためには、「すべてCはかわいそう」などの忖度(これは優しさではなく甘さ)がない評価を行うよう校長から指示していますので、お知りおきください。