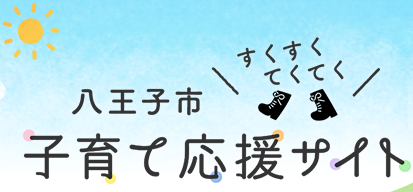11月21日(金)教室の中にある多様性を受け入れ合う(インクルーシブ教育、仲間づくりの場)
- 公開日
- 2025/11/21
- 更新日
- 2025/11/21
学校長より
1クラス35人学級だとすると、個に応じた支援が必要な子は何%程度いると思いますか。
(thinking time)
《写真2》
水…不登校、不登校傾向(12.8%・4.5人)
黄…特異な才能(2.3%・0.8人) 緑…発達障がいのある可能性(7.7%・2.7人)
《写真3》
赤…家に本が少なく低学力傾向(29.8%・10.4人)
桃…家であまり日本語を話さない(2.9%・1.0人)
茶…性同一性障がい・LGBTQ+(4.0%・1.4人)
薄緑…保護者が発達障がいの可能性(7.7%・2.7人)
灰…虐待確認率(1.2%・1.0人)
複数の困り感が重複している子もいるので、必ずしも単純に計算できるものではありませんが、重複しなかったと考えると、個に応じた支援が必要な子の割合は77.1%、35人のうち27人にあたることになります。
そして、色のつかなかった白の8人も、「どのように勉強すれいいのだろうか」とか、「傷ついた友をどう励ませばいいのだろうか」とか、「苦手な仲間とどう接すればいいのだろうか」などと、一人一人が大なり小なり悩みを抱えているはずです。
もしかしたら、「うちの子に特別な支援は必要ありません。普通の子です。」「うちの子がそんなことするはずありません。」という親がいるかもしれません。 この保護者の子には、「『普通でいて当たり前』と思われている親からの無形のプレッシャー」という困り感があると思います。
そう考えると、個に応じた支援が必要な子は、限りなく100%です。
公立学校は社会の縮図です。学区域ごとに小さな小さな社会をつくり出し、9年間をかけて、いくつもの間違いを経験しながら、大人に見守られ、助言を受けて、予測困難な社会を一人で歩むための準備をしているのです。
そう考えると、小学校のうちに、「友達になれるかどうか」という基準ではなく、「多様性の中でいかに仲間としてかかわる力を身に付けられるか」という基準で経験を積ませたいと考えます。ということは、年度替わりのクラス替えは、毎年かなぁ…
すべての子ども、教職員、保護者、地域の方が、「教室の中にある多様性」を認め合える、インクルーシブ教育に先進的な山田小学校を皆でつくっていきたいと思います。
★文中で、「保護者が発達障がいの可能性」と書きましたが、当然ながら教職員や地域の方にも発達障がいの可能性が同程度あると考えています。
★友達と仲間の違いについて、近々話題提供したいと思います。
【参考】
「『初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について』(諮問)参考資料」、「VIEWnext教育委員会版2022Vol.1」、「VIEWnextONLINE」、「子どもの虹情報研修センター資料」