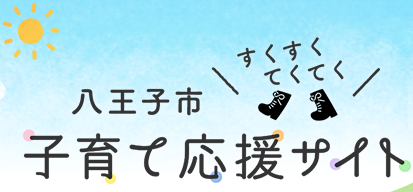11月25日(火)クラスメイトは「友達」というより「仲間」(クラス替えの価値、コミュニケーションスキル向上、非認知能力育成)
- 公開日
- 2025/11/25
- 更新日
- 2025/11/21
学校長より
「友達」と「仲間」の違いについて考えたこと、お子さんとお話ししたことはありますか。
「友達」
○気持ちでつながる、個人的なつながりが中心
・一緒に遊ぶ人、気が合う人、目的がなくても関係が続く人
・プライベートでもかかわる
「仲間」
○目的でつながる、集団的なつながりが中心
・協力して何かをなしとげようとする人たち
・感情の相性と分けながら共通の目標に向かって役割を果たし合う人たち
・プライベートでかかわることはまずない
保護者の方で、小・中学校のクラスメイトと今もプライベートで会うような「友達」はどれくらいいますか。私は、高校まで一緒に進学した一人と、年に一度会うかどうかという程度です。
子どもたちにとっても、学校や習い事から離れたところで、共通の目的があるわけでもなく、おしゃべりのために放課後や週末に会うような「友達」は数人だと思います。
このように考えると、学校は、「友達」を増やす場所ではありません。1年生になっても「友達100人」はできないどころか、一生かけても友達は100人もできないと思います。
学校は、学区域が同じところに、同じタイミングで生を受けたという理由で無作為に集められた「仲間」と、合意形成したり、ちょうどよい距離感を学んだりしながら、目標を達成していく経験を積み重ねていく場所です(これが仲間としての共通目的)。義務教育期間でこの学びを繰り返し、義務教育終了後に社会の中で生きていくスキルを身に付けるのです。
ひとつの学年が81人と想定すると、隔年でのクラス替えの場合は、小学校6年まででおよそ24名(約30%)と同じクラスになることはありませんが、毎年クラス替えをすると、同じクラスになれない子はおよそ7名(9%弱)にまで減ります。
ということは…やっぱり毎年クラス替えかなぁ…
教員など大人に見守られている義務教育期間のうちに、相性が必ずしもよいとは限らない仲間とも、失敗を重ねながら人間関係構築の仕方を学ぶことにとても価値があると考えています。
今のクラスが楽しいという子どもたちにとっては、クラス替えは不安が大きいことも想像できますが、これから年度末にかけて、子どもたちには上記の価値を伝えていきたいと思います。
同じできごとをプラスに捉えるか、マイナスに捉えるかは、子どもたち、保護者の方一人ひとりの内発的な考え方次第です。ご家庭でも、お子さんに学校で身に付けてきてほしい力について、話題にしてみてください。
☆子どもたちのコミュニケーション力は、個人内では年々高まっているはずです。過去のトラブル等でクラス替えの配慮をしていても、改めて仲間としての関係構築にチャレンジをしてほしいものです。複数年にわたって配慮が必要なことについては、毎年2月下旬頃に、保護者が直接担任等にご相談ください。上記の理由から、2月中に相談がなかった件については、過去に相談があった案件であったものであっても、クラス分けの配慮事項とは考えません。
☆写真1・2は、仲間づくりを強く意識していることが分かる高学年の教室掲示です。
☆写真3のようなかかわりが、「いつでも、どこでも、だれとでも」できる心地よさ、距離感を学んでほしいです。