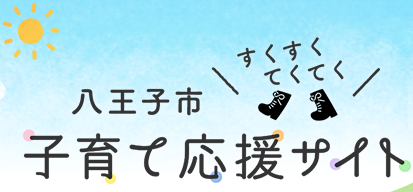11月17日(月)安心できる大人を選んで相談してね(ふれあい月間、全校朝会校長講話)
- 公開日
- 2025/11/17
- 更新日
- 2025/11/15
学校長より
今月はふれあい月間。本日の朝会では、「困ったら一番安心できる大人を選んで相談してね」と話をしました。
子どもは、1日におよそ1万から2万回の選択をしながら生きているとされています。その中には、自分一人で決めるには不安なこと、また、そもそもどうすればよいのかわからなくなることもあるはずです。
そんな時には、安心して相談できる大人を頼ってほしいのです。
相談すれば、解決の道筋が見えるかもしれませんし、少なくとも気持ちが軽くなります。
相談できる大人は、保護者、家族、学校や習い事の先生、サポーター、SC、地域の方など、選択肢はたくさんあります。誰でもいいので、一人で抱えることがないようにしてほしいです。
ただ一つだけ、友達とのトラブルのことや、先生に言われてモヤモヤしたことなど、学校で起こったことは、家に帰ってからもお家の人に話してほしいのですが、家に帰る前に、学校の大人に相談してほしいです。特に相手のあることは、その相手やまわりにいた子にも、その日のうちに話が聞きたいです。
学校では、まずは担任、次に学年の先生、そして専科や保健室の先生、はたまた、クラブや委員会の先生、他にも下学年の時の担任やきょうだいの担任、最後というわけでなくとも、副校長や校長もいます。教員系だけでも、子どもには30近くの選択肢があります。
教職員は、気軽に話しかけやすい、相談しやすい雰囲気がにじみ出るようなソーシャルスキルを身に付けてまいります。
★子どもの意思決定の内訳など(chatGPTより)
1 無意識の決定が多い
○歩く方向、友達に話しかけるかどうか、手を挙げるか、表情の使い方など
○大人と同じように、無意識の自動反応的な選択が非常に多い
2 意識的な決定は少なめ
○「何を食べる」「どんな遊びをする」「どの友達と遊ぶ」など、意識して選ぶ決定は数百〜数千回程度
○学年が上がるにつれて、自己選択の範囲が広がり、意思決定の数も増えていく
3 自己決定の練習段階
○幼児期〜小学校低学年では、決定の多くが大人の指示や環境要因によるもの
○中高学年になると、「自分で考えて選ぶ」比率が増え、意思決定力の発達が顕著になる
★11月の児童虐待防止月間に合わせ、児童虐待や不審者遭遇時の対応についても話をしました。
★自己決定、自己指導能力についても、近々話題提供いたします。
★以下はHPの投稿よりご覧いただけます。