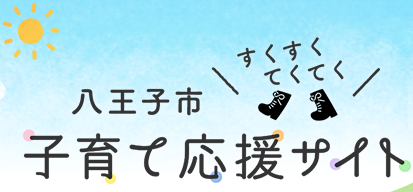11月11日(火)0〜3年目で学習指導力を磨く(教員の資質能力向上、教育実習)
- 公開日
- 2025/11/11
- 更新日
- 2025/11/10
学校長より
先週、八王子市教育委員会の研究主事という立場の方が採用3年次教員の授業指導に来てくれました。
【写真1】4-2研究授業
教科は社会、教科書等の少しの情報をもとに、これまでの学習経験等と関連付けながらたくさんの疑問(調べたいこと)を見付けながら、学習問題と学習計画をつくる授業でした。保護者の皆様が小学生だった頃の学習では、教師主導で調べることも決められていたのではないでしょうか。
今の若手が行う授業はそうではありません!「問い(疑問)」は子どもたちの中から内発的に湧き出てくるものなのです。
どうしたら子どもたちが内発的に問いをもつようになるか、その仕掛けとして何をどのように提示すればよいのかがよく考えられた学習でした。
【写真2】3-2研究授業
教科は国語、前の単元で説明文を読んだ内容に続いて、「話すこと、聞くこと」についての学習です。学校内の各教室等を絵文字(ピクトグラム)に表すことについて考える単元です。この時間は、子どもたちが絵文字(ピクトグラム)にしたい教室等を選び、試しのイラストを描き始める時間でした。描いているうちに、「うまくかけないな」「かきたいけど行ったことない場所だから分からない」などの子どもたちから困り感が表出してきました。
ただ、これは教師が意図的に仕組んだ困り感です。困るからこそ、どうすれば解決できるかを考えるのです。「実際に見に行ってみたい」「校長室のことは校長先生に相談してみたい」「友達(仲間)とも相談したい」など、解決への道筋が内発的に出てきました。
誰が見てもそれとわかる絵文字(ピクトグラム)を相談しながらつくれるかが楽しみです。
研究主事や先輩教員の指導助言を明日からに生かし、よりよい授業を子どもたちに提供することが両教員の使命です!
【写真3】教育実習
先々週までの4週間、大学4年生が教育実習に来ました。担当指導教員が見守る中、たくさんの授業実践を経て、最終週には研究授業と一日担任を経験しました。
翌4月からは、どこかの学校で教員になることでしょう!
教員は、育成・研修期間なく1年目から子どもの前に立に、授業・学級経営を行います。
子どもたちにとっては、その学年は人生一度きりのものですので、「授業や生活指導は、若手だから大目に見てください」とは言えません。
4年目にもなると、「○○主任」など学校運営の分掌業務を任されるようになっていきますので、授業力と生活指導力については、0〜3年目までの間に研修を積んで十分に身に付ける必要があるのです。
数年後の学校教育の中核を担う若手教員の育成も学校組織に課された大切なタスクです。写真にあるように、学年の主任教諭をはじめ、校内多くの教員が授業準備、授業観察、授業後の振り返りを通して指導助言を行っている姿が嬉しいことです。