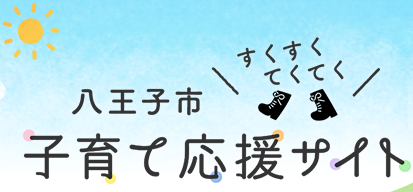11月18日(火)子どもの話と学校や他者の話の「ずれ」が子どもと保護者の生きづらさ(主観的現実と客観的事実)
- 公開日
- 2025/11/18
- 更新日
- 2025/11/17
学校長より
★以下の文章の「保護者、親」は教員や友達などの周囲の人と置き換えることもできます。
お子さんがお家で話す学校での出来事やトラブルなどについて、保護者の皆様はそれを「主観的現実」だと一歩引いて捉えられていますでしょうか。
子どもは自分の都合の悪いことを保護者に話さないことが往々にしてあります。これは、保護者が善悪に厳しすぎる場合や、保護者の期待に応えなければならないと必要以上に感じている場合に多くなる傾向にあります。
「本当のことを言ったら親に怒られ、嫌われるかも」「親を悲しませるかも」と思ってしまうのです。
子どもが親の前で都合の悪いことを隠すのは、親をだまそうとか、学校や友達を貶めようとかいう心理が先に来るわけではありません。
「自分の間違い、弱さ、苦手さを許してもらえないかも」という不安や「話を大きくすれば、忙しい親が心配してくれるかも」という思いから、事実を多少なりとも脚色した「主観的現実」をつくりあげることがあります。
(例:被害の側「後ろから背中を殴られて倒れた」←→加害の側「ポンと背中を触ったらびっくりしたのか転んじゃったみたい」)
そして、この「主観的現実」は、親などに「そうだったんだね」とあたかも事実だったかのように認定されると、本人にとっても、それが本当にあったこととして上書きされてしまったり、「昨日の話と違うじゃん」と言われるのが怖くてもう言い直せなくなったりしてしまいます。
この状態になってしまうと苦しいのは、その子どもと保護者です。
客観的事実を知っている周りの子などとの「認知のずれ」の中で生きていくことになり、時に「よくうそをつく子」などと認定されてしまいかねないのです。
この状態を防ぐために、保護者が気をつけることは…
1.「主観的現実」と「客観的事実」を分けて考えるくせをつけること
2.平穏な日々にこそ、「大好き」「あなたのままでいい」「間違えたら一緒に謝ろう」と子どもに伝え続けること
3.子どもの話(主観的現実)を聞いた際に「✖️そうだったんだね(事実認定)」と返すのではなく、「⚪︎そう感じたんだね(気持ちへの共感)」と返すこと
4.お子さんの立場と異なる子の保護者仲間や学校の見解に耳を傾けた上で「客観的事実」を探ること
5.客観的事実と主観的現実にずれがあり、他者との話合いが必要となった場合は、保護者が謝罪や改善点を相手に伝えている様子を子に見せること
子どもが本当のことを話せる相手は、自分の失敗や弱さも含めて受け入れてくれる、自分を愛してくれていると実感できる人だけだと思います。そして、それは誰よりも保護者であるべきです。
教員も、お子さんの言動を保護者の方に伝える際には、可能な限り客観的事実として情報提供ができるように努めてまいります。