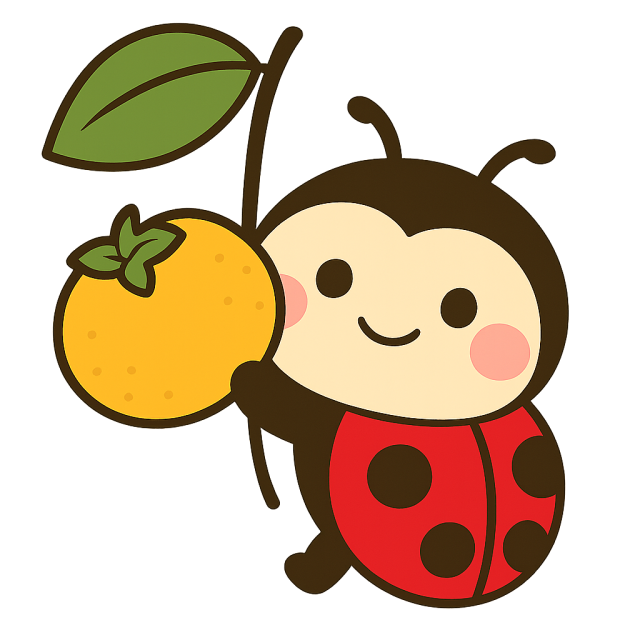教員の働き方改革へのご理解とご協力をお願い申し上げます
- 公開日
- 2025/09/28
- 更新日
- 2025/09/26
市役所・行政・生活指導・防犯だより
9月30日といえば一般の人にはなじみがないのですが、東京都の学校では大きな節目の日となります。
令和7年度東京都公立学校教員採用候補者選考(8年度採用)の最終合格発表日になります。小学校で35,244人、中学校で15,891人、高校で9,560人、特別支援学校で6,647人の先生が働いいています。東京都の教員だけで約67000人もいるので、企業に例えると、全国に事業所があるパナソニックやKDDI、日本通運などの大手企業などと同規模の従業員が先生として働いていることになります。
これだけの教員がいると、毎年、定年や病気などで退職をする教員もたくさんいて、その補充を毎年4000人程度募集をかけるのです。
しかし、一昔前まではこの募集に何十倍もの応募者が殺到し、優秀な教員を採用することは難しいことではありませんでした。
ですが、近年は状況が変化しつつあります。その原因はいくつかありますが、下記の2点が大きな要因といえます。
・教員に限らず、国内全業種で人数が足りていない
・教員の働く環境に魅力を感じていない人が増加した
前者の内容は日本の構造そのものなので、教育界全体では如何ともしがたいのですが、後者については早急に対策が必要といわれています。
そこで、近年叫ばれているのが「働き方改革」なのです。
〇教員の働き方改革
学校の先生は業務内容が多く忙しく大変。
労働時間と給与が見合わない。
教員以外の他業種の方が魅力がある。
こんな声が大学生の中で広がる状況で、教員採用試験の応募倍率は下がり、教員不足に歯止めがかかりません。
このままでは、子どもへの悪影響が懸念される深刻な状況となっています。
そこで、先日、国会で関連する教員の働き方改革に関する法律の改正が行われ、新たな指針の案が示されました。
〇指針案の内容は? 教員の仕事を誰に分担?
指針の最大のポイントは、教員が担う業務を軽減させないといけないということです。
教員を志す人の多くは自分の学んできた知識や経験を子どもたちに還元したい。
すなわち授業が教員の主な業務となるべきなのですが、現実はそうなっていません。
社会全体が学校や教員に多くの期待を寄せていく中で授業という主業務を阻害している現実があるのです。
わかりやすくいうと、カーボンニュートラルを地球規模で推進しようとします。
⇩
日本国内でも国際社会のこうした動きに連動した動きをする。
⇩
しかし、将来的に社会全体を変えようとするには、目の前の大人に周知するよりも未来を担う子供たちこうした教育を推進しようとなる⇩
⇩
すると、今までの授業内容に
・「カーボンニュートラル」の学習内容=授業案作成・授業準備
・「カーボンニュートラル」の研究者や実践している人たちの講演=団体折衝・講演会準備・謝金申請・打ち合わせ
・「カーボンニュートラル」の体験活動や施設見学=事前調査・実施計画作成・保護者説明・当日の引率
・「カーボンニュートラル」の調査や発表=実施計画作成・授業案作成・発表準備指導
といった学習が増加していきます。そうなれば、多くの人たちと教員は打ち合わせや準備に時間が割かれていきます。
何かが学習内容としてなくなれば差し引きゼロですが、今まで通りの授業は変化しないケースが多いので単純に学習内容は増えていきます。
こうやって、学校すなわち教員の負担増へとつながっているのです。
そこで、今回の指針案では、時間外勤務について、
・月45時間を超える教員をゼロにすること
・年間の平均は月30時間程度を目指すこと
などが数値目標として盛り込まれています。
そしてそのために、現在教員が担っている仕事を減らしたり、ほかの立場の人に分担したりする例を3つにわけて示しています。
「業務の3分類」と言われるもので
・学校以外が担うべき業務
・教師以外が積極的に参画すべき業務
・教師の業務だが負担軽減すべき業務
です。代表例として示されている19項目のうち、一部を見ていきます。
《学校以外が担うべき業務》
・給食費や教材費など「学校徴収金」の徴収・管理は教員ではなく、自治体などが一元管理する
→ 八王子市では事務並びに市役所が担っています
・学校への不当な要求などへの対応は、教育委員会や弁護士が担う体制をつくること
→ 八王子市ではスクールロイヤー制度が導入されています
《教師以外が積極的に参画すべき業務》
・学校の広報資料やホームページの作成・管理
→ 副校長補佐などが担う学校が増えています(本校は副校長が頑張っています)
・児童や生徒にひとり1台配布されている端末などICT機器の保守・管理
→ 八王子市ではICT支援員などが配置されています
・部活動は地域などに移行
→ 八王子市では部活動改革が来年完成します(本校はすでに完了しています)
《教師の仕事だが負担軽減すべき業務》
・修学旅行など行事の日程調整や準備
→ 行事の見直しはこれに関連した内容で市内ではスキー校外学習がなくなっていっています
・就職先の情報収集など進路指導の準備
→ オンラインの活用やアウトソーシングが行われていっています
・支援が必要な子どもへの対応はスクールカウンセラーなど専門的な立場の人とともに行う
→ 八王子市ではSSWの活用などもはじまっています
ただ、この指針案が示された文部科学省の中央教育審議会の特別部会では、委員から
「実現には人や費用が必要で、国としてもそうした環境整備を進めるべきだ」という指摘が相次ぎました。
【学校の事務職員とは? 代わりに担える?】
八王子市の学校には事務職員が東京都からと八王子市からの2人配置されています。
施設保守には用務主事が1人配置されています(学校規模による)。
事務職員は自治体によっては1人、下手すると配置されていない地区もあります。
これは、行政単位の税収に比例しているのが現状です。教員の業務量が軽減しても、事務職員の業務量過多になってしまっては意味がありません。
今までに学校にいなかった職員も増えています。
副校長補佐と呼ばれる職員やスクールサポートスタッフ(SSS)、部活動指導員、スクールカウンセラー(SC)という職員もその代表例です。
学校サポーターや校内別室指導支援員、部活動指導補助員といったボランティアも学校の運営を担ってくれています。給食の配膳員も同様です。
こうした多くの学校を支えるチーム学校の一人一人が気持ちよく働けることで、子どもたち一人が安心して通える学校がつくれるものと信じています。
今後とも保護者ならびに地域の皆様におかれましては、こうした実情をご理解いただき、持続可能な学校に向けてご理解とご協力をお願い申し上げます。
写真の内容は八王子市教育委員会が示した教員の働き方改革に向けたリーフレットです。